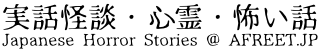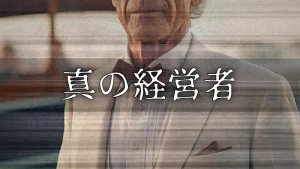栃木県 会社員 恩田隼人(54)(仮名)
「ステージ4ですね。5年生存率は5%ほどです。」
医者に事務的に告げられたのは、42歳の春でした。
忙しさを理由に、のらりくらりと健康診断をサボってきた私は、去年の冬、とうとう会社の上司に叱責され、イヤイヤ検診を受けたのですが、異常が認められたため、再検査となったのです。
様々な精密検査の後、待っていたのは、まさかの胆管ガンという診断と、「5%」という、虚しい数字でした。
「なんで俺が? 仕事も家庭も順調だった。自分で言うのもなんだけど、他人には優しく接してきたし、子供が出来てすぐにタバコもやめた。その俺が一体何したっていうんだ? 5年後に生きていられる確率がたったの5%って、どういうことなんだよ!」
怒りや悲しみ、恨みといった、この世に存在するであろう全ての負の感情が、毎朝起きてから夜寝るまでの間、次から次へと心の中にとめどなく湧き上がりました。
知り合いの勧めで、ガンの治癒率が高いと噂されている病院に転院しました。
転院後も、見舞いに来てくれた家族や会社の同僚たちには、精一杯の作り笑いで弱みを見せないよう努めるのですが、それがまたストレスとなって、私はとうとう自ら命を絶つことまで考えるようになっていました。
今考えれば、人というのはつくづく不思議な生き物です。
放っておけば5年以内に95%の確率で死ねるというのに、必ず手の届く死を前にすると、自らそれを引き寄せ、命を絶つ道を模索するのです。
当時の私は、それほどまでに追い詰められていたのかも知れません。
そんな考えに囚われている訳ですから、当然治療にも消極的でした。
精神的な作用もあるのでしょうか、薬の効果もほとんど得られず、毎日少しずつ病気に飲み込まれていく自分を実感していました。
そんなある日のこと、ついに私は死に場所を求めて、病院の屋上へと上がって行きました。
どうせ死ぬのだからと、10年前、妻が長男を妊娠した時からやめていたタバコの煙を、ゆっくりと肺の中一杯に吸い込んだ時、子供のために必死で禁煙したことや、その後、女の子が生まれたこと、入学式や幼稚園の発表会などの思い出が、まさしく走馬灯のように思い出され、自然と涙が溢れてきました。
「これ、吸い終わったら逝くか・・・」
人生最期の感傷に浸っていたその時、どこからともなく現れた子供が、急に私の真後ろから声をかけてきました。
「おじさん。死ぬの?」
危うく腰を抜かしそうなほど驚きました。その女の子は、上の子と同じくらいの背格好でしたので、たぶん小学校4、5年生でしょう。
パジャマを着ていましたから、きっとこの病院の入院患者だろうと思いました。
「お嬢ちゃん、ここは子供が入ってはイケナイところなんだよ。すぐ病室に戻りなさい。」
「おじさん、病気? もしかして、ガン?」
ズケズケと、面白そうに質問を繰り返すこの子に、さすがの私も少し腹が立ちました。
「おじさん、泣いてんの? 大人なのに? ふぅ〜ん。
あたしはね、最後まで泣かなかったよ。
だって、泣いたら周りの人の方が悲しむでしょ。
だから、あたしはガマンしたの。」
その時、女の子の「最後まで」という言葉がなんだか引っかかりましたが、子供の言うことだと思い、聞き流しました。
「おじさんはなんで泣いてんの? 奥さんのため? 子供のため?」
「全部だよ。」
「うっそー、違うよー。自分のためでしょ? 自分が可哀想なだけでしょ? だって奥さんも子供も、おじさんに泣いて欲しいなんて思ってないでしょ? おじさんが泣いたら、みんな余計に悲しくなるじゃん。だから、おじさんがここで死んだら、きっともっと、今よりずっと悲しくなると思うよ。」
女の子の言葉が、今まで自分では届かなかった胸の奥深くにグサグサと突き刺さりました。
「あと、せっかくやめてたんだから、タバコはもう吸わないほうがいいんじゃない?」
そう言い終わった女の子は、階下につながるドアの向こうへと帰って行きました。
「あの子の言うとおりだ・・・あんな子供に諭されて・・・俺は一体何をやってるんだ?」
私は身勝手な考えに囚われていた自分を、心底恥ずかしく思い、持っていたタバコの箱とライターを、そのままゴミ箱に捨てました。
自分の病室に戻り、枕の下の遺書を破り捨てながら、冷静になって考えると、私がタバコをやめていたことを、あの女の子がなぜ知っているのか、不思議に思いました。
しばらくすると、検温のため、看護師長さんが巡回してきました。
私はさっきの女の子のことが気になり、何となく師長さんに聞いてみました。
「師長さん、小学校4年生くらいの、ピンクの花柄のパジャマを着ている、ショートカットの女の子は、何の病気ですか?」
すぐにバカなことを聞いてしまったと反省しました。そんなことは個人情報だし、教えてもらえるわけがないのです。
ところが、その看護師長さんは、当たり前のように、その子について話し始めたのです。
「ああ、恩田さんもサオリちゃんに会ったのね。サオリちゃんはかれこれ20年以上前に入院してたんだけど、とっても強い子でね。進行性の小児ガンで相当痛かったでしょうに、泣いたら負けだって言ってね。大人でも根を上げるようなきつい薬を使っても、最期まで、頑張って頑張って、頑張り抜いて、泣き言ひとつ言わなかったんですよ。」
師長さんの「最期まで」という言葉に、その子がどうなったのかは想像がつきました。
そのサオリちゃんは入院中、看護師さんの目を盗んでは、度々屋上に上がって、空や雲、星を眺めていたそうです。
当時、病院側は安全管理のため、屋上の施錠・閉鎖も考えたそうですが、サオリちゃんのことがあったため、どうしても閉鎖できなかったのだそうです。
何よりも驚いたのは、看護師長さんが、20年前にこの病院で亡くなった女の子と私との関わりを、まるで良くある日常の出来事のように話してくれたことです。
その後、私は弱い考えを改め、治療にも積極的になり、その結果、医者も驚くほどの奇跡的な回復を遂げ、数ヶ月後には晴れて退院できることになりました。
もし、悪い考えに囚われたままなら、きっと今の私は存在しません。
今考えると、屋上に出入り自由な病院など、かなり珍しいのですが、屋上から誰かが飛び降りて自殺したといったことも全くない上に、いわゆる「生存率」は、他の病院に比べて圧倒的に高いそうです。
もしかしたら、あの時屋上で出会ったサオリちゃんは、亡くなった後、天使になって、今でもあの病院の屋上で、病気に負けてしまいそうな患者たちを励まし続けているのかも知れません。