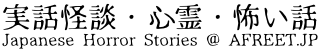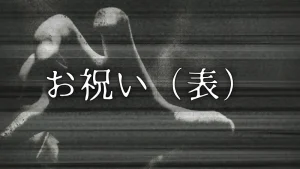どうやらそれは、霊能者に教えてもらった、呪いの儀式なんだそうです。
「自分じゃできないから、翔くん、これで私の爪、抜いて」
彼女は買ってきたばかりのペンチをプラスチックのパッケージから取り出し、私の目の前に突きつけると、テーブルの上に左手を置き、動かないように反対の手で抑え、身構えました。
「いやいやいやいや! 無理無理無理無理! そんなの絶対無理だよ!!」
必死で断る私に、彼女は冷淡な座った目で私を睨みつけて、こう言いました。
「じゃあ、私と一緒に・・・死ぬ?」
彼女の覚悟は本物でした。
彼女はサッとタオルを口に咥え、頬を紅潮させ、ギュッと目を瞑ったまま、右手で掴んだ左手を私の前に差し出し、微動だにしません。
だた、その時、彼女の肩は、恐怖で少し震えていました。
「わかった・・・ ごめん・・・ 行くよ!」
私は渾身の力を込めて、彼女の親指の爪を剥ぎました。
「ングッ!!」
彼女の小さな悲鳴が、口に咥えたタオルを通して聞こえてきました。
彼女の爪が、思ったより力なくズルっと抜ける感触は、今でもこの手に残っています。
私と彼女は、この恐ろしい儀式を、親指から小指まで、全部で5回繰り返しました。
その後、彼女の左手に絆創膏と包帯を巻き、彼女に言われるがまま、呪い袋を一緒に作りました。
「これを・・・俺が部屋の中に隠しておけば良いの?」
私の問いに、彼女は答えました。
「そう。でもね、翔くんが隠しちゃダメ。私の爪と髪だから、私が自分で隠さないとダメなの」
その翌週、ホームパーティーの日を迎えました。
彼女はごく自然な動きで、1つずつ呪い袋を隠して行きます。
「この後、一体どうなるんだろう?」
私は今後の展開を、全く予想することができずにいました。
翌日、自分の部屋を掃除している時に妻の悲鳴を聞きつけ、リビングに行ったところ、すでに1つ目の呪い袋が発見されていました。
その後、「まだあるから」と言われ、一緒に探すフリを続けましたが、結局、妻は合計4つしか、呪い袋を発見できませんでした。
さらに、どうもそういう時の「女の勘」というのは神がかり的で、犯人はAさんしかいないということになり、交際していたことも白状させられ、2時間以上正座させられたまま、こっぴどく叱られる羽目になりました。
ところで、妻に見つかった呪い袋は全部で4つです。
という事は、まだ1つ、見つかっていない呪い袋が、うちのどこかにあるはずです。
もちろん、本命の彼女は、その在処を教えてくれません。
それからというもの、私がこの計画の首謀者の一人であることがバレてしまうのではないかと言う恐怖から、妻の言うことにはできるだけ逆らわないようにしています。
そう言えば、「祝う」と言う字と「呪う」と言う字は、少し似ていると思いませんか?