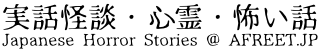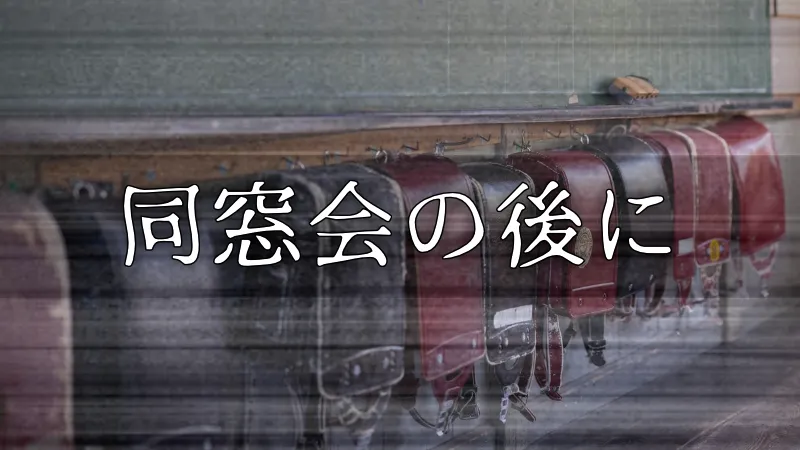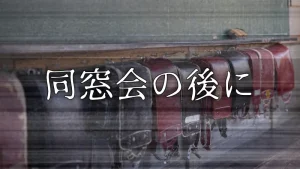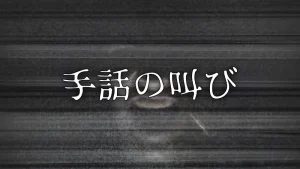東京都 会社員 石田遼(29)(仮名)
母からの電話で、私が住んでいた村でも少子化が進み、通っていた小学校が廃校になることが決まった、という知らせを聞いたのは、その年の春でした。
戦前から改修を重ね、戦火を逃れ、続いてきた歴史ある小学校です。ましてや母校の廃校となれば、時代の流れとはいえ、何とも切ないものでした。
その年の夏のことです。
私同様「母校廃校」のニュースを聞きつけた同級生たちから、校舎が無くなる前に地元で同窓会をしようという企画が持ち上がりました。
私が在籍していた当時は、1学年全体で13名しかいなかったので、同窓会と言っても、ちょっとした飲み会レベルです。
それでも同級生のほとんど全員が参加することになり、帰省前に母に頼んで送ってもらった卒業アルバムを見ながらニヤニヤしたり、仕事中に思い出した当時のエピソードについついニンマリしてみたり・・・そんな日々を送るうちに、指折り数えた同窓会当日を迎えました。
私が暮らしていた村は、「ド」がいくつも付くような、正真正銘の田舎です。
もちろん、村には飲食店などありませんから、一番大きな旧家に住む同級生の実家の、20畳もある大広間を借りて、持ち寄った郷土料理やつまみ、酒などで、大いに盛り上がりました。
村に残って家業を継いだ者。
街へ出て就職した者。
夢の実現のために、今はアルバイトで頑張っている者。
中でも東京で働いているのは私だけでしたので、「遼はスゴイ!出世頭だ!」ともてはやされ、なんだか少しくすぐったい気分でした。
久しぶりに楽しい酒を飲むうちにすっかり夜も更け、1人帰り、2人帰りしてそろそろ終宴の雰囲気がただよって来る中で、最後まで残ったのは私を含め、一番仲の良かった男3人と女2人、合計5人の悪ガキグループでした。
夜中の1時を回った頃、また廃校になる母校の話題になったとき、友人の一人が言いました。
「ねぇ、今から小学校、見に行かない?」
「いいねぇ」
「御意」
私は酔っていたこともあり、「明日みんなで一緒に見に行く約束だっただろう。もうこんな時間だし、明日でいいじゃんか」と言いかけたのですが、他の連中は完全に乗り気だったので、場をしらけさせるのも悪いと思い、渋々行くことにしました。
小学校までの道のりは、歩けば大人でも30分はかかります。街灯もなく、月明かりだけが頼りの田舎道です。
昔通い慣れた通学路とは言え、こんなに遠かったか、こんなに細かったか、などと思いを巡らせながら、フラフラとおぼつかない足取りで、ジャングルの中の1本道を歩き、山道を抜け、小高い丘に沿って細い道を左に曲がるとスーッと視界が開け、正面に懐かしの母校が現れました。
フェンスで囲われた校庭を挟んだその向こう側に、久しぶりに見る木造平屋の古びた校舎が目に入った時、私の胸にはなんとも言えない懐かしさがいっぱいに広がり、一緒に歩いてきた友人たちも皆、その眼前に広がる悠久の景色に思わず立ち止まり、それぞれの思い出を、この田舎の空気と一緒にゆっくりと味わっているようでした。
「懐かしいなぁ・・・」
「うん。全然変わってないね・・・」
「屋根って、あんな感じだったっけ?」
東京の蒸し暑さに慣れてしまったせいでしょうか。少し冷たくさえ感じる山の風が、とても心地よく私をなでて行きました。
フェンス伝いに右側に周り、少し歩けば懐かしの母校の正門です。
左手に校舎を見ながら正門へ向かう途中、友人の一人がいぶかしげに言いました。
「あれ? 教室、電気点いてない?」
「ホントだ。なんかちょっと明るいね」
目を凝らすと、2つ並んだ教室のうち、右側の教室だけ、小さなランタンでも灯したかのように、青白くボーッと光っているように見えました。
ただ、不思議なのは、電気が消えているなら教室の中は真っ暗で、何も見えないはずです。
「電気は・・・点いてないよ。それならもっと明るいはずだろ?」
「誰かいるのか?」
「もう夜中の2時前だぜ。こんな時間に誰かいる訳ないだろう」
歩きながら近づいていくと、見えないはずの教室の中が少しずつ見えてきたその瞬間、5人の足取りがほぼ同時に止まりました。