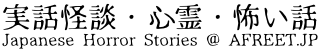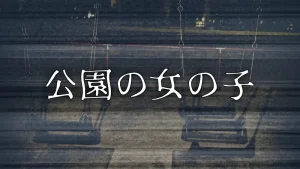埼玉県 保育士 A.Mさん(26歳・女性)の恐怖の体験談
当時、私は保育士になるため、大学に通っていました。
大学は駅から徒歩10分ほどで、途中にある小さな公園を斜めに抜ければ、少しだけ近道ができます。
ただ、建物と植栽に挟まれたその公園は昼間でも薄暗く、とても陰気で、以前、焼身自殺があったとか、夜は痴漢が出るといった噂もありました。
その上、園内の遊具も、駅側の入り口を入って右奥の死角に、赤いブランコがポツンと2つあるだけで、子供が遊んでいる姿など、ほとんど見たことがありませんでした。
だから私も、その公園を抜けるのは、どうしても講義に遅刻しそうな昼間だけ。そう決めていたのです。
ある蒸し暑い、梅雨空の日でした。いつもの時間に乗った電車が、途中で止まってしまったのです。車内には、沿線の大雨の影響で電車が遅れるというアナウンスが流れました。
運悪く、その日は前期の試験日だったので、私は祈るような気持ちで運転の再開を待っていると、10分ほどで電車が動き出しました。
駅に着くと雨は上がっていました。私は急いで改札を抜け、小走りで大学へ向い、あの公園の前に差し掛かりました。
出入り口から公園の中の様子を伺うと、いつにも増して暗く鬱蒼としていて、蒸し暑い日にもかかわらず、何だかゾクッとするような寒気を感じました。
「このままじゃちょっと遅刻かな・・・朝だし、よし、大丈夫!」
私は自分にそう言い聞かせ、大きく吸った息を止めている間に、一気にその公園を走り抜けることにしました。
一息で公園を抜けた後、ふと後ろを振り返ると、紺色のワンピースを着た女の子が、奥の赤いブランコに、一人で座っていました。
「あれ? さっきもあの子、いたかな?」
こんなに蒸し暑い雨上がりの公園で、女の子が一人・・・少し違和感を覚え立ち止まっていた私は、ふと我に帰り、急いで学校に向かいました。
幸い試験にも遅れずに済み、そのあと6限目まできっちり講義に出席して、帰る頃にはすっかり日も暮れていました。
友人と一緒の帰り道、またあの公園の前まで来た時のことです。
暗い公園の奥で、たぶん、今朝と同じ女の子が、あの赤いブランコに座っているのが見えました。
「え? 朝からずーっとここに? まさかね。」
私の独り言に友人が
「美佳、どうしたの?」
と尋ねてきたので、公園の外に立ち止まったまま、朝の出来事を話しました。
友人は
「あんな小さい子が、朝から同じ場所にいるはずないよ。」
と言って、歩き始めましたが、私はどうしても気になって、公園の中を横切り、女の子の方へ向かって歩き出しました。
私が一人で公園に入って行くのに気付いた友人が、小走りで追いかけてきて、私の腕を掴んで言いました。
「ちょっと、美佳、どこ行くの?」
「うん、あの子のこと、ちょっと気になってね。」
友人に腕を掴まれたまま、女の子の前まで来た時、私はハッとしました。
遠目からでは分からなかったのですが、その女の子の紺色のワンピースは、明るい色ならもう着ることができないほどシミやほつれだらけで、背中まである長い髪は、何日も梳かしていないのが分かるほど、ツヤもなく広がっていました。
その子の雰囲気に、友人も言葉を失っていましたが、私は思い切って、その女の子に話しかけてみました。
「こんにちは。こんばんは、かな? お嬢ちゃん、ひとりで遊んでるの?」
女の子はうつむいたまま、何も答えません。
「お姉ちゃんね、美佳っていうの。お嬢ちゃんは? お名前は?」
やはり何も答えてくれません。
「もう暗くなってきたから、お家の人が心配してるんじゃない? お家は? 近いの?」
すると女の子は、公園を取り囲む金網の向こう側にある建物を、無言のまま指差しました。今まで意識しませんでしたが、その建物は以前から大学へ行く道沿いにある、古いアパートでした。
女の子の家が近かったことで、私は少しホッとしながら、一番気になっていたことを聞きました。
「ねぇ、もしかして、お嬢ちゃんは朝からずーっとここにいたの?」
すると女の子は、首を何度か横に振った後、初めて弱々しい声を出して答えてくれました。
「…ちがうよ…」
その時、その言葉に被せるようにして、友人が私の右腕を引きながら言いました。
「もういいでしょ。美佳。行こう。」
私は後ろ髪引かれる思いでしたが、女の子に「じゃあね、バイバイ。」とだけ告げて、友人に引きずられるようにして公園を後にしました。
その後、私は友人とファミレスで夕飯を食べながらも、あの女の子のことが頭から離れませんでした。
「ねぇ、あれってもしかしてネグレクトじゃないかな? 服とか髪とか見たでしょ? ほら、講義で今、件数は増えてるけど表面化しにくいって言ってたし。だとしたら、児童相談所とかに通報した方がいいんじゃないかな?」
「もう、美佳、いい加減にしときなよ。それぞれの家には人それぞれ、事情があるんだよ。他人の家のことにあんまり首突っ込まない方がいいって。」
友人に諭されながら、私はこういう時の、講義で習うのとは違う現実世界での対応の難しさを、身をもって痛感しました。