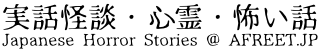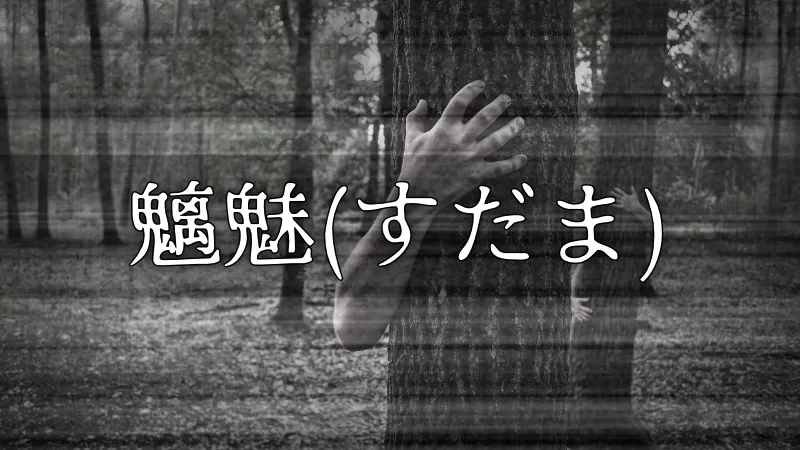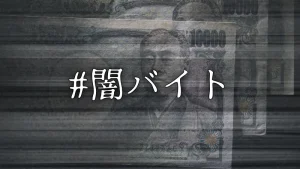岡山県 主婦 藤井 愛(38)(仮名)
私が小学校2年生の時の体験談です。
その頃私は、岡山県の山の中に暮らしていました。
隣の民家まで優に200メートルはあるような、正真正銘の田舎です。
学校に通うのも、行きは下り坂なので40分ほどですが、帰りは登り坂を1時間近くかけて毎日通っていました。
ある日、学校から帰ってきた私は、親戚の家まで、お使いを頼まれました。
その親戚の家は、私の家の裏手から伸びる1本道を、川沿いに20分ほど歩いたところにあります。
秋も深まる頃の夕方、太陽が少しずつ傾き、山の陰に半分ほど隠れると、あたりは一気に暗くなります。
できるだけ明るい内に帰りたかった私は、母に頼まれた品物を親戚のおばさんに手渡し、「ご褒美に」と渡されたお菓子と缶ジュースが入った紙袋を抱え、急いで山道を下って行きました。
家までの道のりを半分ほど歩いた頃です。
「コロン・・・ コロン・・・」
と、鈴のような音色が聞こえてきました。
滅多にないことですが、この辺りでは熊が出ることもあるので、山の奥で仕事をする人は、熊除けの鈴を慣らしながら歩くことがあります。
だとすると、誰かが歩いて山を登って来たのかな? と思った私は、暗くなって行く山道で、一人ぼっちではないことに、少し安心しました。
急なカーブを曲がり切ったところで、道のずっと先に、鈴の音の主が登ってくるのが見えました。
その姿を見た時、私は妙な胸騒ぎを感じました。
この時期、この時間帯になると、山の気温は急に冷え込みます。
それなのに、視線の先を歩いて来る人は、膝上くらいの短い浴衣のような着物を着ているのです。
それに、この道を通る人は限られていて、知らない人が歩いていることなど、まずありません。
それなのに、少しずつ近づいて来るその人は、明らかにこの辺りの住民ではなく、見たことのない人でした。
初めは道の向こうに小さく見えたその人影も、お互いに歩いて進むにつれて、次第に大きくなり、表情が見えるほどにまで近づきました。
「わー、やっぱり知らん人だ」
私は目をそらし、その人をやり過ごそうとしたのですが、その人は道の左側を歩く私の進路を塞ぐように、スーッと左側へ寄ってきたのです。
私はとても怖かったのですが、思い切ってうつむき加減だった顔を上げて、その人の顔を見ました。
年の頃は30歳くらいの、若い男性だったと思います。
浅黒い顔に、ギョロッと大きな目で、汚れた髪を頭のてっぺんに丸く束ね、コケてくぼんだ頬に挟まれた口元に、イヤらしい笑みを浮かべ、そこから黄色く汚れた歯が覗いていました。
目があった途端、その人は
「右側においでなさるか? 左側においでなさるか?」
と、男性とも女性とも、子供とも大人ともつかない、不思議な声で聞いてきました。
この辺りで会う人は、みんなクセの強い岡山弁なのですが、その人は標準語に近いような、聞いたことがないイントネーションで話しかけてきたことが、より一層、気味の悪さを掻き立てました。
怖くなった私は、何も答えないまま、道の右側に避けて通ろうと思ったのですが、その人はすぐに私と同じ方向に体を寄せてきます。
今度は左に寄ろうとすると、やはり通せんぼするように、その男の人は左に避けてきます。
よく見ると、その男の人の着物はとても薄汚れていて、もう何年も洗っていないように見えました。
そう思った瞬間、その男の人は、着物の襟の部分を摘んで引っ張りながら、
「これね。 これ、上等よ。 一番上等よ」
と、薄気味の悪い声で言いました。
私はもう、怖くて怖くて、とにかくこの男の人をかわして、道の向こうへ行きたいのですが、私が左右に進もうとすると、その都度絶妙のタイミングで、私が先に行くのを邪魔して来るのです。
私は恐怖で泣きそうになりながら、男の人の足元を見ました。
とても汚れたその足は、右足には大きな白い鼻緒の男性用のゲタを、左足には赤い花柄の鼻緒が付いた、黒い女性用のゲタを履いています。
それを見た瞬間、またその男の人は
「足? そこの沢でキレーに洗ったんよ。 だからもう沢の水は、飲まんほうがいいよ」
と言いました。
まるで私の考えていることを見透かしているように、私が心の中で思ったことについて、その都度言ってくるのです。
さらに、その男の人は続けて
「こっちはハマジさんのゲタよ。 こっちはハルミさんのよ」
と、片足ずつ差し出すようにして言いました。
「ハルミさん」は聞いたことがありませんでしたが、「ハマジさん」は林業をしている父と一緒に働いていた同僚で、何ヶ月か前に山の事故で亡くなった人の名前でした。
「コワイよ・・・ どうしよう・・・」
怖さで震えながら目に涙を溜め、なんとか逃げる方法はないかと考えていた時、おばさんからもらった紙袋の底が破れ、中の缶ジュースが地面に落ちました。
その男の人が一瞬、坂道を転がって行く缶ジュースを目で追った瞬間、私は一目散に坂道を駆け下り、一度も後ろを振り返ることなく家に着きました。
家で私の帰りを待っていた父と母にその話をすると、父は真っ赤な顔で激怒し、大きなナタを持ってその男の人を探しに走り出しましたが、1本道の終わりまで行っても、見つけることはできなかったそうです。
それからしばらく経って、親戚のおばさんにその話をすると、それはこの辺りに昔から住み着く「魑魅(すだま)」と言う妖怪の仕業だと言われました。
言い伝えでは、魑魅魍魎(ちみもうりょう)の魑魅(ちみ)と書いて「すだま」と読むその妖怪は、山林の瘴気(しょうき)、つまり人々を病気にさせる毒気から発生する魔物であると言われ、山中で人を迷わせ、魂を奪うのだと聞いて、私は改めてゾッとしました。
それから半年ほど経った時、家のすぐ脇を流れる、とても綺麗だった沢の水が、上流の砂防ダム工事の影響で、茶色く濁ってしまいました。
あの時の「沢の水は、飲まんほうがいいよ」と言う言葉は、このことを予言していたのでしょうか。