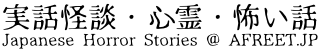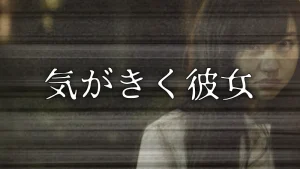東京都の会社員Mさんが、社会人になった今でも忘れられない、恐ろしい体験談です。
当時、俺には毎年更新し続けている記録がありました。それは、『彼女いない歴』です。
岐阜の田舎町から2浪の末、「モテそう」という幻想から東京のミッション系の大学に入り、憧れの一人暮らしと花のキャンパスライフを夢見ていましたが、現実はそう甘くはありませんでした。
入学と同時にスポーツ系のサークルに入ったのですが、そこはいわゆるチャラ系のサークルで、金曜になるとほぼ隔週で合コンが開催されました。
元来、女性が苦手というわけではないのですが、この金曜の恒例行事は、全くモテない俺にとって、単なる苦役でしかありません。
当時、学費と生活費は、共働きの両親が苦労してなんとか工面してくれましたが、さすがに遊興費までは無心できず、週末の飲食店でのアルバイト代も、ほとんど合コンで消えてしまうような生活が丸1年ほど続いていて、そんな生活に疑問を感じていた頃でした。
新学期を迎え、春の憂鬱な金曜日のことでした。
その日の合コンも、あまり気乗りしなかった俺は、店に入ってすぐ、テーブル左奥の窓際に陣取り、ひっそりと時間が経つのを待つ作戦でした。
「このサークルもそろそろ辞めどきかな?」
はしゃぐ友人を尻目に、そんなことを考えながら、ぼんやりと窓の外を眺めていると、20分ほど遅れて女性陣が合流しました。
すると、その中のひとりが、「ここ、いいですか?」と言って、俺が座っていた場所のさらに奥の、狭い隙間を指差し、立っていたのです。
座ったまま見上げると、胸の前で束ねた黒く長い髪が印象的な、とても清楚な感じの美人でした。
彼女はテーブルと壁との10センチくらいの隙間を通って、俺の左側に回ってきたことになります。
内心「ずいぶん細い子だな。」と感心しながら、「あ、もちろん、どうぞどうぞ。」と、右側にいた友人の体をグイッと押しのけてスペースを作り、そこにその子を座らせました。
俺と壁との隙間に挟まるようにして座っていた彼女は、とても気がきく女性で、俺のお皿が空になるとすぐに食べ物を取り分け、お酒がなくなりそうになるとすぐに飲み物を取ってくれました。
「名前、聞いてなかったよね。俺、マサノブ。佐藤雅信。君は?」
「ユイです。」
「ユイちゃんか。ごめんね。ここ狭くない?」
「あ、全然、大丈夫ですよ。」
そう言う彼女の返事の雰囲気さえも、なんだか可愛く、愛おしく思えました。
その時俺は、きっとこの日のために、たぶんこの娘に出会うために、このサークルに入ったのだと思いました。
いつものお開きが待ち遠しい合コンと違い、今日は時計の方が狂っているのではないかと思うほど、あっという間に時間が過ぎました。
「どうしよう、ここで何とか連絡先とか交換しとかないと・・・」
焦り始めた俺の気持ちを察したのか、やはり彼女は本当に気がききました。
「マサノブさん、連絡先、聞いてもいいですか? だめ?」
もう、死んでもいいと思いました。いや、死んだらもう彼女に会えない。むしろ死ぬまで生きたいと思いました。
彼女は今時珍しく、携帯を持っていませんでしたが、そんなことにすら何だか、清楚で可憐な印象を受けました。
俺は彼女に吸い込まれていくような感覚に陥りながら、携帯電話の番号と、聞かれてもいないアパートの住所まで教えてしまいました。
「うわ、ヤバイ・・・クッソカワイイ・・・」
俺の言葉を一生懸命、丁寧に丁寧にメモっている姿は完全に天使でした。俺の魂は、完全にユイちゃんに飲み込まれてしまいました。
合コンがお開きになった時、2階の店から階段を下り、男性陣と女性陣は1階で左右に別れて帰りました。
その時も、女性陣が「バイバイ」とあっさり手を振って一斉に駅に向かって帰って行く中で、ユイちゃんだけは一人その場を動かず、姿が見えなくなるまで、俺たちの、いえ、俺だけの姿を見送ってくれました。
翌朝、俺は人生最大のミスを犯したことに気づきました。
ユイちゃんの連絡先を聞いていなかったのです。
「・・・オレ・・・マジ・・・バカか・・・ユイちゃんから連絡来なかったら、もうアウトじゃんか・・・」
その影響からか、俺はその日1日、食欲もなく常にぼんやりとしていて、夕方からのバイトも凡ミスの連続でした。
夜9時を過ぎた頃、バイトが終わって帰宅しました。
ミスが多かったせいか、その日はいつもより疲れているような気がしました。
風呂にでも入ろうかと思ったその時です。「ピンポーン」とドアチャイムが鳴りました。
「こんな時間に。宅配便か?」と思い、ドアスコープから確認すると、そこにはスーパーのレジ袋を持った、ユイちゃんが立っていたのです。