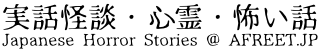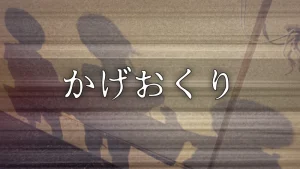ドアが開くのを待ち構えていたかのように吹き込んで来た冷気と、顔を刺すような氷の礫の向こうに広がった光景に、まず最初に驚いたのは、このわずかな時間で降り積もった雪の深さでした。
私がこの小屋に入ってから、わずか10分ほどの間に、ヒザ下ほどの雪が積もり、あたりは一面の銀世界になっていたのです。
その状況にドアを締めることも忘れ、すっかり呆けてしばらく立ち尽くしていましたが、わざわざ痛い足を引きずってまでドアを開けに来た目的を思い出した私はすぐに正気を取り戻し、ドアを叩いた人物の姿を探しましたが、周囲には誰もいません。
ただ唯一、間違いなく誰かがそこにいた証拠に、雪の中に足跡が、ドアに向かって左右対にくっきりと付いていたのです。
でもそれは、絶対にありえないことでした。
足跡からは地面の土や砂利が、そのまま覗いています。
つまり、雪が積もる前から誰かがずっとそこに立っていないと、このような足跡は付かないはずなのです。
更に不可解なのは、この足跡に続く足跡が、どこにもないことでした。
来た足跡も、帰った足跡も、何一つ残っておらず、ただ左右一対の足跡が、そこにポツンと残されているという状況に、ゾクッと怖気が立ったのは、外から吹き込んでくる冷気のせいだけではなかったはずです。
私はすぐにドアを閉め、足が痛いことも忘れ、走ってシュラフの中に潜り込みました。
シュラフの中で最初に頭に思い浮かんだのは、もしもう一度ノックの音が聞こえたらどうするか、ということでした。
次に思い浮かんだのは、ノックの音がドアから小屋の周りを1周して、あるいはノックする音が次第に増えていって、あるいは小屋の屋根の上から・・・
ありもしない妄想は私の中で肥大化していきました。
私は自らの脳内で勝手に作り出した恐怖の幻想に苛まれながら、いつの間にかシュラフの中で眠りについていました。
朝日が小屋の中を明るく照らす頃、頭までかぶったシュラフの中の熱気で汗だくになった私は目を覚ましました。
目を覚ました途端、シュラフから這い出る前に、また妄想が始まりました。
「あれは夢・・・? いや、絶対に夢じゃない! あのノックの主が、もしこの小屋の中にいたら・・・ もし小屋の中を埋め尽くすほど大勢いたら・・・」
シュラフの隙間から片目でそっと小屋の中を見回しましたが、私の心配を他所に、そこには誰もいませんでした。
ホッとしてシュラフから這い出て、首筋の汗を手で拭い、早まった鼓動が収まるまで一息ついてから、小屋の外の様子を見ようと決心するまで、かなり時間がかかったように思います。
くじいた足の痛みが強くなっていないことを確認し、靴を履いてゆっくりとドアに近づき、震える手をドアノブにかけ、勢い任せに思い切り引っ張ると、冷たく新鮮な空気と同時に、信じられない光景が私の目に飛び込んできました。
「あれ? 雪が・・・ ない!!」
この気温であれほど降り積もっていた雪が、一晩で綺麗サッパリ溶けてなくなることなど、考えられません。
岩の周りや木の根の影など、少しくらいは残っているはずの雪が、どこにもまったくないのです。
その後、私は下山しながら、これらの一連の体験についてずっと考えましたが、自分が納得できるような結論にたどり着くことはできませんでした。
私はきっと、狐か狸にでも化かされたのでしょう。
もしそうだとすると、これもやはり私にとって、初めての経験となりました。